社会的な課題に氣付き、意識して買い物をすることを「エシカル消費」といいます。
もう少し詳しく言うと、あなたの日常の買い物が生産者さんに、地球環境に、消費者に配慮した優しいものであるのかを考えた消費活動のこと。
そしてこれからの未来を見据えた、持続可能な暮らしやエシカル消費を心掛けるときに、ぜひ知っておきたいのが「グリーンウォッシュ」です。
今回はこの「グリーンウォッシュ」について、何が問題でどのように見分ければいいのかについて掘り下げてお伝えします。
✓グリーンウォッシュと実例
✓グリーンウオッシュを見分ける方法
✓なぜグリーンウオッシュを意識するのか
「グリーンウォッシュ」とは

グリーンウォッシュは、エコや自然をイメージさせる「グリーン」とうわべを取り繕うなどの意味の「ホワイトウォッシュ」を掛け合わせた造語。
実際にはそうではないのに、いかにも環境に良さそうと思わせて、購入に促すような商品や広告を一度は目にしたことがあるかもしれません。残念なことですが、ブランドイメージの向上やビジネスのために、コピーやデザインを駆使してそのような表現が使われていることは事実。
SDGsに注目が集まる今だからこそ、環境意識の高い消費者を、あの手この手で(結果的に)騙そうとするビジネスが生まれているのでしょう。
問題はどこにある?

グリーンウォッシュの問題点は、本質からずれている点。
本当に環境に配慮した消費やサービスが報われず、実態を伴わないグリーンウォッシュの企業が不当に高い評価を受けてしまうこと。
そうすることで、消費者は地球に優しいと思って使い続けていた商品が、実はそうではなかった。もしくは逆効果だった、ということもあり得るのです。
ヨーロッパではグリーンウォッシュの広告を審査する機関があるそうですが、残念ながら日本では厳しい規制などはまだないようです。
だからこそ私たちは、自分の買い物により意識的になる必要がありそうです。
過去の実例
グリーンウォッシュといえば「マクドナルド」を、思い浮かべる人もいるかもしれません。
2009年にヨーロッパの「マクドナルド」が、赤と黄色のロゴを緑色に変更したのです。これが「グリーンウォッシュではないか」と国民から指摘を受けました。
ロゴの色を自然を彷彿させる緑にしただけで、実際には環境保護や改善への取り組みがあるわけではなかったことで、この案件は「マクドナルド」のイメージアップのためだけに行われたグリーンウォッシュと言えます。
ほかにも「キンバリー・クラーク」の売り出したおむつの、「環境に優しい、ピュアでナチュラルなおむつ」という謳い文句。実は材料に、石油化学商品のゲルが使われていたのです。明らかに不適切な表現だと問題になりました。これも消費者を騙し、不当なイメージアップを図った事例ですね。
見極めポイント・チェックリスト10!
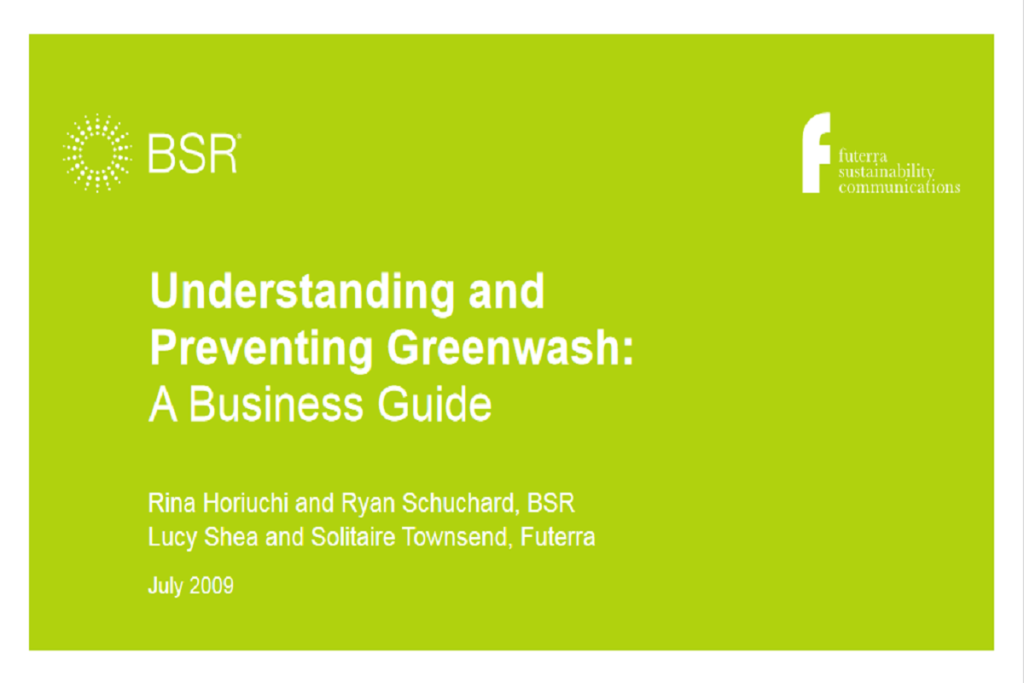
source by 「futerra」
イギリスの「Futerra社」は、グリーンウォッシュを防ぐために、「Understanding and Preventing Greenwash:A Business Guide」というガイドを発行。
そのなかでグリーンウォッシュを疑うポイントが、10個掲載されています。これらがある場合は、要チェックという目安に覚えておきたいですね。
1:Fluffy language(あいまいな表現)
「エコフレンドリー」などのあいまいな言葉を使っている。
2:Green product vs. dirty company(グリーンな商品と汚れた会社)
例えば効率のいい電球を開発・製造している会社が、環境負荷をかけている。
3:Suggestive pictures(示唆させる絵)
いかにも環境に良さそうなデザインや写真を使っている。
4: Irrelevant claims (的外れな主張)
ほかが全てエコでなくても、一点だけいいことをしていたら過剰に誇張する。
5: Best in class (クラスで一番)
業界ナンバーワンと謳うが、その業界自体が全体的にエコ意識が低い場合。
6:Just not credible(単に信頼に値しない)
環境に優しいタバコ、のように安全性のないとされるタバコをグリーン化する。
7: Jargon(わかりにくい表現)
科学者や専門家にしかわからない言葉や情報を使う。
8: Imaginary friends(架空の友)
〇〇認証・●●推薦などのラベルの、第三者を自社で作り出している。
9:No proof(証拠なし)
エビデンス、根拠のない情報。
10: Out-right lying(あからさまな嘘)
捏造されたデータ。
注意したいのは、本当にエコに配慮した商品もそのようなヴィジュアルやコピーを使うことがあるということ。
その見極めは難しいのですが、今ではウェブサイトで検索することもオンラインで問い合わせも簡単にできる時代。本当に気に入って使いたい、その会社を応援したいのであれば確認してから、が良さそうです。
最後に
こういう情報に触れると、ますます何を信じればいいのと思いがちに。
大事なことは、諦めないことと直感を信じることだと思います。
「信じて買ったのに、騙された」と残念に思ったとしても、その経験は必ず次の買い物の糧になるのです。そして繰り返すうちに調べ方、自分なりの見極めポイントがわかってくるはずです。
あいまいな表現を鵜呑みにしない、耳障りのいい言葉は裏があると疑う、商品を作っている企業の信頼性をリサーチする、原材料をしっかりと確認する。
こんなことを書いていると、自分を疑ってばっかりのひねくれ者みたいに感じます。笑
でも私たち日本人は、今まであまりに従順だった気がするのです。
売れればいい、と考えている企業も残念ながらたくさん存在します。
あなたとあなたの大切な家族、そして私たちが住む地球環境のために、今までよりほんの少しだけ本気で消費活動に取り組んでみませんか。




コメント