今、時代は「情報戦争」とも言われるほど、ありとあらゆる情報が散乱しています。テレビ、口コミ、インターネットなど場所もさまざまです。
「食で健康を保つこと」は、いつからこれほど難しいことになったのだろう、と思います。
良いと言われていた食材でも、別の情報では否定派がいたり…。「じゃあ、どうすればいいの?」となっている人も、本当に多いのではないでしょうか。なにより、そうやって情報に振り回される時間は心も疲弊してしまいます。
「ストレスは食べ物の何倍も、体に対して毒になる」と読んでしっくりきた私は、それ以来「食べることをストレスにしない」をモットーにしています。
じゃあどうすればよいのか、それは究極、自分の感覚に頼るしかないと感じています。その感覚の生かし方、そして食の「軸」をどう持つかのヒントを5つ紹介します。
※私は食のエキスパートでも専門家でもありません。「食学検定」で食養学とマクロビを少し学び、オーガニック料理ソムリエで日本の食の現状を少し学び、あとは独学と勘です。そのため鵜呑みにはせず、ですがぜひ参考にしてみてくださいね
✓健康関連の情報の多さに疲弊している
✓自分と身近な人の健康のためになにかしたい
✓行動は起こしていないけど、食生活を改めたいとは思っている
「食」に対しても、自分軸を持つことの重要性
「これを食べれば体にいい!」というものは、もはや存在しない(と、あえての言い切り)!
本来はいいとされるものでも、今は栽培や加工の方法などで、その食材そのものの力は100%発揮されていない。つまり私たちが摂取しても、その食材が持つ成分や栄養素をそのまま取り込めるわけではない、ということをまず理解しておきたいですね。
そしてさらに言うなら、私たち一人ひとりの体質や体調で、その人によっても違う、その人のその日によっても違うのだから、やはり「これさえ摂っておけば!」という万能な代物はないと言えるでしょう。
1. 基礎知識は本から
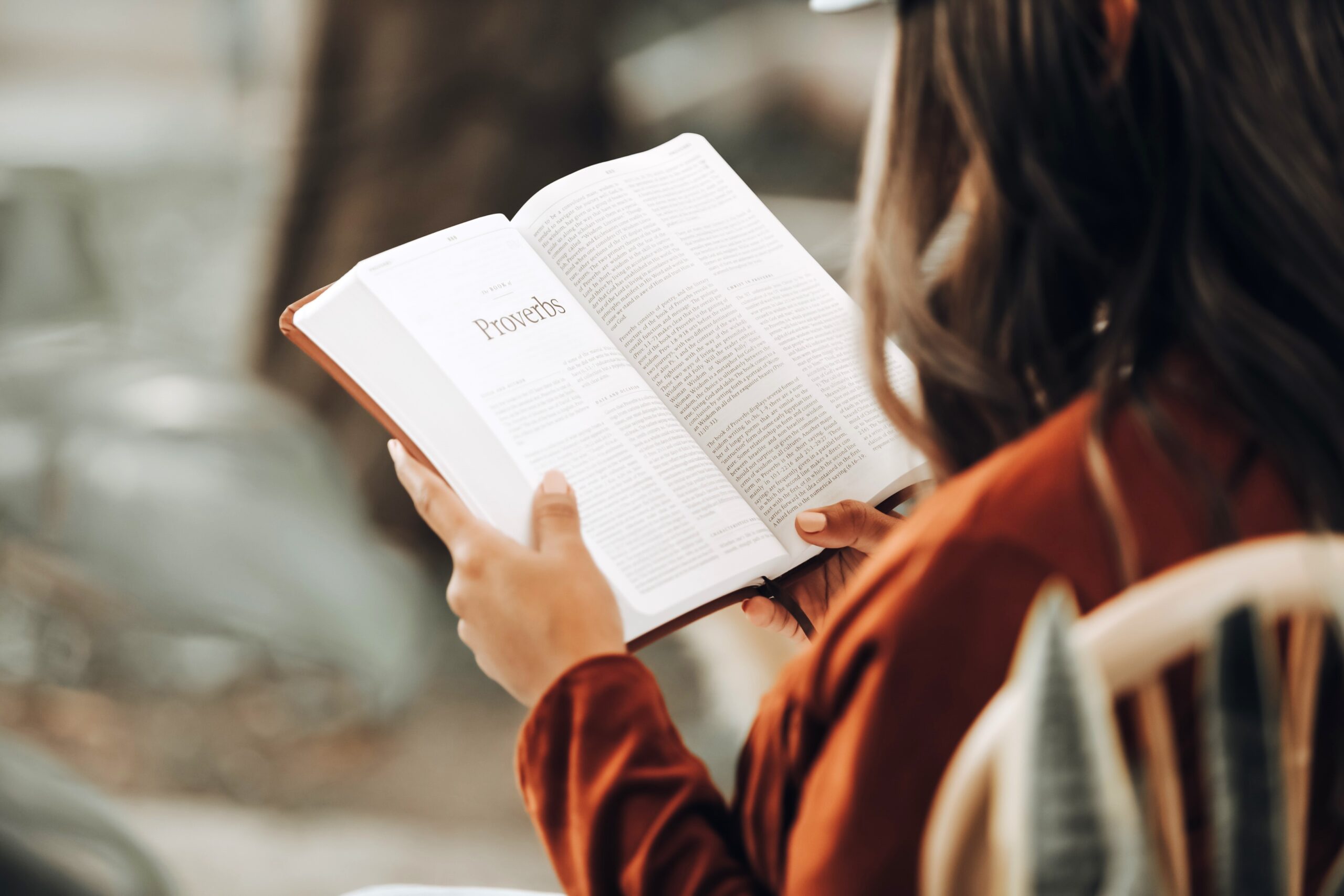
本がまた万能ではないことも、たびたび指摘されています。
ですが、「見る人を導くために編集された情報」であるテレビよりは誠実で、多くの人の目と事実確認(校閲)が入ったものであることは間違いありません。それは今、web媒体で書く私が、かつて紙媒体の制作を手がけていたために、少しはわかる事実です。
本を読みましょう!不変の真実は、名書とされる書籍のなかにきっとあります。
食に関する書籍は多くありますが、おすすめをまとめて記事にします。
(ここに貼る予定!)
2. 原材料を見るクセをつける

内容の一語一句がわからなくてもいいので、とにかく手に取った商品がなにから作られているのか、なにが入っているのかを「知ろうとする」こと。まずはそこからです。
そして、もし原材料のラベルに書いてある言葉の意味がわからなかったら、それこそが不自然なものかもしれない、と違和感に気づくことが大切。なぜなら本来、私たちが口にする食品はもっとシンプルでいいはずなのです。
例えば家でお菓子を焼くとき、余った野菜を使い焼き飯を作るとき、調味料はとてもシンプルですよね?砂糖に小麦粉、重曹、そして塩コショウ、醤油など…。
ではなぜスーパーやコンビニのお惣菜やお弁当には、あれほどおびただしい数の「意味不明ななにか」が入っているのでしょう。カタカナや数字で書かれた名前は、よくわからない。それは、あなたの勉強不足だけが問題ではないのです、本来入らなくていいものが入っている、ということかもしれないのです。
もちろん、それらに目を通した後に買い物かごに入れるのは、なるべくシンプルな原料で作られたもの。そしてできれば、国産の原料のものを選びましょう。
※食品添加物のクラスを受け、食の専門家の意見を聞いたこともあります。食品添加物は、食品を「より多くの人に届けたい」「より長い間食べられるようにしたい」という想いから生まれたものですが、今では経済的な理由となっている部分が大半で、食べる人の健康は二の次。その部分にも私は違和感を感じています
3. 知っている作り手から買う

すべてができているわけではありませんが、「知っている作り手から買う」ことも、私のなかで大切にしていること。できれば作り手、つまり製造者ですね。難しければ作り手とつながっている販売者でもいいでしょう。
私は信頼できるお気に入りの飲食店が数件あるので、外食はそのなかをローテーションで回っています。食材も販売しているためそこで買うか、もしくはそのお店の人と仲良くなり、そのお店が信頼している別の作り手や販売者を聞き出すというのも手です。
だいたい、心ある自然派の飲食店のほとんどは「健やかな食生活を広めたい」という想いが根底にあるため、快く教えてくれますよ!
「Money Voting(買い物は投票)」という言葉もありますが、やはりこれからの買い物は特に、残って欲しいお店や取り組みにVote(投票)したいものです。
4. 実際に試す

実際に食べて自分の体で試してみることも、今後も食べ続けるかどうかを決定するひとつの手段となります。
自分の体に合うものは、食べた後に胃もたれしない、体が重く感じないどころか軽く感じる、恒常性(オホメタシス)が快適に保たれる、などがあります。
この辺も、自分の感覚に頼る部分がありますので、普段から自分の体がどういう状態&感覚かを把握しておきましょう!
5. 自分の体を信じる

冒頭で「ストレスは食べ物の何倍も、体に対して毒になる」と書きましたが、心配も同じです。「これを食べても大丈夫かな?」「肌荒れ(やほかの症状)悪化しないかな?」などと思って食べると、その心配通りの症状を引き起こしやすくなります。
「心配」や「不安」というネガティブな思いは、免疫機能を下げると言われてもいますし、なにより、その思いが自分のフィルターとなり設定となり、自分の現実を創造してしまうことは間違いないのです。
私が取り入れているのが、設定・前提を自分の望むものに上書きする!という方法。
これは私にとって、本当に効果があります!「私が食べるものは、すべて私の体に良く作用する」とか、「私の体は不要なものを排出する力がある」などです。アファメーションと呼ばれるものに似ていますが、これを口に出したりして自分の細胞にしみ込ませています。
なぜ効果があるとわかるのか、というと、実践するほどに「思い込もう」としなくても、体のなかから「大丈夫!」という力がみなぎってくるから。この、自分の奥から発される想いほど力強いものはありません。そしてそういう想い(つまり波動)が、私の体に作用する現実が創られるのです。
-
情報にまみれて、なにを食べたらいいか迷っている人に、少しでもヒントになればと思い書きました。
個人的に、今必要なのはもう知識(だけでは)ではないな、と感じています。それはこの3年なりのパンデ〇ックを通して、より明白になりました。どれほど情報を調べたとしても、パソコン上では真実にたどり着けない…。
ましてや「食」に関することは、器がそれぞれ違うのと同じように、ひとつの答えなどありえませんよね。だからこそ、私たちは自分の持っている力を信頼する必要があるのです。直感、感覚です。
もちろん、それがいかんなく発揮されるためには、逆説的ですが専門家からの学びや「よく知ろうとする姿勢」はとても大切。偏らず、ニュートラルにホリスティックな立ち位置から、ものごとを見て感じてみることで、自分にとってなにが必要かは見えてくるのでは、と思うのです。
もし、この文章にピンときたら、ぜひ参考にしてみてくださいね!




コメント