フード(食品)ロスとは、まだ食べられる食品を廃棄すること、また廃棄された食品を指します。
この概念は、日本でもずいぶんと浸透してきました。
2030年の目標達成を目指したSDGsを、国や世界ぐるみで進めているのもその理由のひとつです。
年末という、人々が集いいたるところで会食が開かれる今の時期に、改めてフードロスについて考えてみませんか。
✓フードロスの現状
✓フードロス対策への考え方
✓今日からできる個人のフードロス対策
✓フードロス対策をしている企業
食品廃棄の現状

UNEP(国際連合環境計画)の「 Food Waste Index Report 2021」によると、世界の食品ロス(フードロス)は9億3,100万トンでした。ちなみに2020年度の日本国内の食品廃棄の量(フードロス)は約522万トン。
これはどちらも年々減少しており、国内においては10年前(2012年)の642万トンより120万トンも減少しています。
それだけ企業努力はもちろん、私たち一人ひとりの意識が変化し、できることを日常的に取り入れているのがわかりますね。
フードロス対策の2R+アップサイクルの考え方

フードロス・食品廃棄を無くすためには、ゼロウェイストの5Rの考え方がとても有効です。
フードロス対策に関しては、こちらの2R。さらに今、多くの企業が取り入れている、アップサイクルも追加します。
2. Reuse(すでにあるもの・買ったものは「使い回す」)
3. Upcycle(新しい価値を付けて再利用する)
例えば1.であれば、お土産やサンプルなど相手の方は「良かれと思って」と渡される食品など。もし好みが違う、食べる予定がないなら「気持ちだけ」と丁寧に断ることも大切です。また買い物などで買い過ぎないことも、1.に含まれます。
そして2.は食品を食べ切る工夫、などがこれに当たります。一度で食べ切れない場合は、保存食にすることや喜んでくれる人にプレゼントするなど、捨てる前に工夫できることは色々とあります。
3.に関しては、特に企業などが本来捨てられる廃棄物を使って、新たな価値を付けて販売するなどのアップサイクルな取り組みが目立ちます。
個人ではできなくても、こういった企業の商品を選ぶ(=購入する)ことでフードロス対策に参加していることになります。
世界のフードロス対策

食品の廃棄を出さない法整備|フランス
企業という括りではなく国としてフードロス対策をさらに真剣に取り組んでいるのが、フランスです。
フランスでは2016年、まだ消費できる食品の廃棄禁止や、売れ残りの食品は大型スーパーを対象に慈善団体などへの寄付、家畜の肥料・農業用の堆肥として転用することが義務づけられ、法整備して積極的に取り組んでいます。
廃棄直前の食品を扱う「OzHarvest Market」|オーストラリア
オーストラリアのシドニーにオープンしたのは、そんな廃棄直前の食料ばかりを集めたスーパーマーケット「OzHarvest Market(オズハーベストマーケット)」。
同スーパーは2004年、Ronni Kahn AOが自身のイベントで廃棄される大量の食品に気づいたことがきっかけで設立されました。慈善事業のためではなく、明らかな問題解決の手段として廃棄直前の食品を、地元の慈善団体に届けたことが始まりでした。
運営は基本ボランティアにより行われ、売り上げは彼らの活動費に充てられます。ただこの売上ですが、値段はすべて買い手が決めるのだそう。なかなかユニークな方法ですよね!
不完全な食品を格安で!宅配も「Imperfect Foods」|アメリカ
「Imperfect Foods(インパーフェクト・フーズ)」は、規格外の野菜果物などを農家や生産者から買い取り、スーパーでの販売価格の約30~50%引きで通信販売しています。つまり、こだわりのまだ美味しく食べられる食品を安価で購入でき、自宅まで配送してくれるという、買い手にも嬉しいサービスなのです。
食品はオーガニックとそうでない栽培方法のものが、買い物のたびに選べるのもメリットです。
国内のフードロス対策

「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」
2018年、自治体間のネットワーク「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」が発足。
「おいしい食べ物を適量で残さず食べきる運動」に賛同する地方公共団体によって、広く全国で食べきり運動等を推進し、3Rの推進と共に食品ロスを削減することを目的として設立されました。
発信内容、活動内容は自治体により異なります。
小売店舗で「てまえどり」呼びかけ
国内では消費者庁で、小売店舗で消費者に「てまえどり」を呼びかける啓発を行っています。これはもちろんフードロスを防ぐために、これからすぐ食べるなら手前から取りましょう、ということ。
賞味期限がギリギリのものばかりが売れ残ることを、防ぐためです。
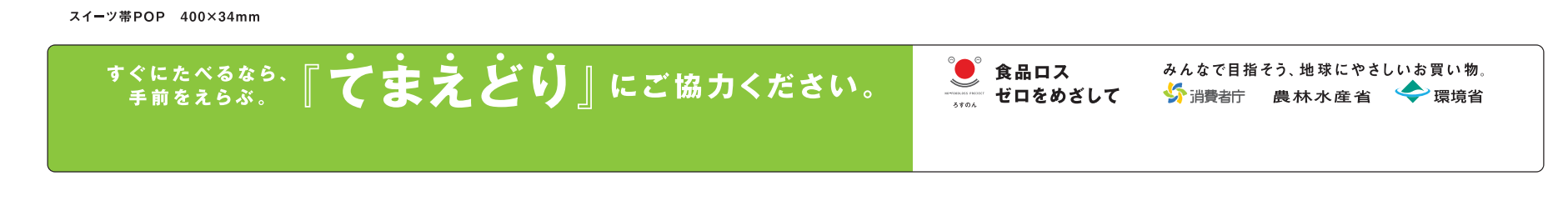
こういう帯やポスターを、コンビニなどでも目にするようになりましたよね。
フードシェアリングアプリ「TABETE」
「グッドデザイン賞2019」のベスト100にも選出された「TABETE(タベテ)」。
このフードシェアリングアプリは、まだまだおいしく食べられるのに「捨てざるを得ない」食事/食品を、ユーザーが1品からお得に購入することによって「レスキュー」できるという仕組み。
出品されているのは、まだ美味しく食べられるにもかかわらず売り切るのが難しい食品です。「TABETE」を通した購入は、食品ロス削減アクションにつながります。
2022年3月の時点で、登録者数が50万人を突破、登録店舗数も中食業態を中心に2,000店舗に到達しています。時代の需要と供給がマッチした取り組みと言えますね。
パン好きにはたまらない「rebake」
rebake(リベイク)は、パン専用のフードシェアリングアプリ。
パンに特化しているため、こだわりの多いパン好きの人も好みの作り手が見つけやすいのも魅力ですね。また通信販売のため、家にいながら買い物が完結!店に出向いて商品を引き取る必要はありません。

以前、取材させてもらった神戸の老舗ベーカリーもロス対策で利用していると話されてました
-
取り組みや仕組みとして、フードロス対策をすることも今となっては必要不可欠となってしまいました。そしてそれらを積極的に利用することも…。
でも日本では昔から浸透している考え方、「もったいない」精神があります。
米粒ひとつにも神様が宿るとされていた、その想いをベースにした消費活動に私たち一人ひとりが戻すことで改善される部分も多いにあるような気がします。
【参照】UNEP Food Waste Index Report 2021
【参照】我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和2年度)の公表について
【参照】COLUMN8 フランスにおける食品ロス削減の取組
【参照】国内最大級の食品ロス削減サービス「TABETE」の登録者数が50万人を突破。登録店舗数も中食業態を中心に2,000店舗に到達。





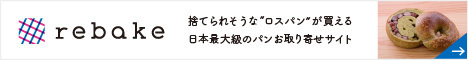


コメント